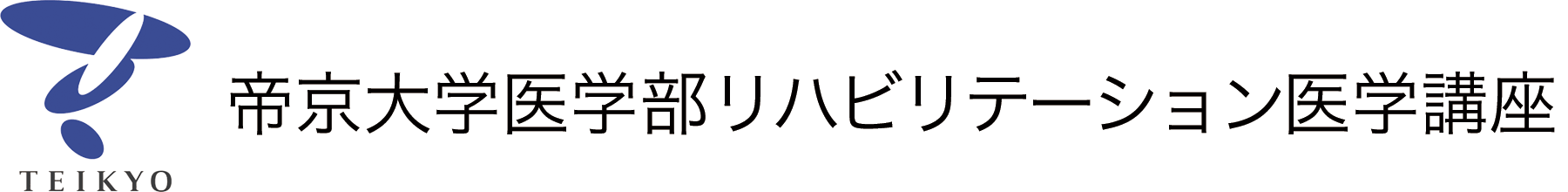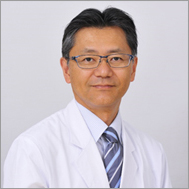ご挨拶
帝京大学医学部リハビリテーション医学講座のホームページにアクセスして頂きありがとうございます。2014年(平成26年)7月より帝京大学医学部リハビリテーション医学講座(当時、帝京大学リハビリテーション科)とリハビリテーションセンターの責任者を務めさせていただいている緒方直史よりご挨拶申し上げます。
当講座の歴史は、昭和47年に東京大学より帝京大学整形外科に着任された岩倉博光先生が、昭和52年にリハビリテーション部教授に就任され独立した診療業務を行うようになったのが始まりです。リハビリテーション科自体はまだまだ歴史の浅い分野ですが、帝京大学では昭和57年にリハビリテーション科が正式に開設されており、東日本の大学病院ではリハビリテーション科が標榜された5番目と、リハビリテーション科の中では比較的歴史が古い大学です。
平成2年(1990年)から、2代目として三上真弘教授が引き継がれ、当講座の基礎を築かれました。三上教授は第14回義肢装具学会(1998年)、第39回日本リハビリテーション医学会(2002年)、第31回顔面神経研究会(2008年)など多くの会長を務められ、当科の発展に尽力され、帝京大学医学部附属病院の病院長も務められました。
平成20年(2008年)から、3代目として栢森良二教授が務められました。栢森教授は顔面神経麻痺の診断と治療、リハビリテーションの基礎を築かれ、日本一の症例数を誇っておられました。平成21年(2009年)5月から帝京大学医学部附属病院は新築され新病院での診療が始まり、リハビリテーション部はリハビリテーションセンターとなり、診療科であるリハビリテーション科と隣接した場所で診療業務を行うこととなりました。それまでは、診療科として病床を20床ほど持っておりましたが、回復期リハビリテーション病棟の制度が出来てからは診療科としての病床は2床となっています。
そして平成26年(2014年)から、4代目として私が責任者を務めさせていただいております。その間多くのリハビリテーション医が育ち、リハビリテーション医学の発展に貢献してくれています。
現在10名のリハビリテーション科医がおり、リハビリテーション診療に関わる関連職種も27名の理学療法士と7名の作業療法士、3名の言語聴覚士で急性期リハビリテーションに対応すべくチームを組んで日々奮闘しているところです。
リハビリテーション医学は高齢化社会に突入している日本にとって、切っても切り離せない領域であり、まだまだこれから伸びていく数少ない診療科です。専門医の数もこれだけ回復期リハビリテーション病院が増えていく中、2200名ほどしかおらず圧倒的に不足しています。リハビリテーション医療での診断・治療がどれだけまだ必要とされているか、まだまだやるべき事の多さ、リハビリテーション医学が可能性を多く秘めた分野である点は大変魅力的だと思いますし、未来あふれる診療科だと思っています。
最後にこのホームページが、これまで帝京大学リハビリテーション医療・医学に関わって下さった方、あるいは今後関わる可能性のある多くの方との橋渡しになれば幸いです。また、帝京大学リハビリテーション科では、若い先生のあふれる力を必要としています。これからのリハビリテーション医療を牽引していこうと思うぐらいの多くのやる気があり、未来のある若手医師、リハビリテーション関連職種が仲間に加わってくれることを期待しています。
沿革
| 昭和52年 (1977年) | 昭和47年(1972年)に帝京大学整形外科に着任された岩倉博光先生がリハビリテーション部教授に就任され、独立した診療業務を行うようになりました。 |
| 昭和57年(1982年) | リハビリテーション科(当時は理学療法科)が正式に開設され、岩倉教授が初代教授・科長に就任されました。これは関東で3番目に早い開設です。 |
| 平成2年 (1990年) | 2代目として三上真弘教授に引き継がれました。 三上教授は第14回義肢装具学会(1998年)、第39回日本リハビリテーション医学会(2002年)、第31回顔面神経研究会(2008年)の会長を務められ、帝京大学医学部附属病院の病院長を務められました。 |
| 平成20年 (2008年) | 3代目として栢森良二教授が務められました。 |
| 平成21年 (2009年) | 5月から帝京大学医学部附属病院は新築された新病院での診療が始まり、リハビリテーション部はリハビリテーションセンターとなり、診療科であるリハビリテーション科と隣接した場所で診療業務を行うこととなりました。 |
| 平成26年 (2014年) | 4代目として緒方直史教授がリハビリテーション科科長に就任しています。 |
| 令和2年 (2020年) | 4月に講座化いたしました。 緒方直史教授が主任教授に就任しています。 |
リハビリテーション科医、リハビリテーション科専門医とは?
日本リハビリテーション医学会ではリハビリテーション科専門医とは、「病気や外傷の結果生じる障害を医学的に診断治療し、機能回復と社会復帰を総合的に提供することを専門とする医師」と定義しています。
リハビリテーション科専門医の業務は、疾病や障害の診断・評価・治療、リハビリテーションゴールの設定、理学療法、作業療法、言語聴覚療法、義肢・装具等の処方、運動に伴うリスクの管理、リハビリテーションチームの統括、関連診療科との連携など、多彩です。
診療の対象となる疾患・障害も幅広く、脳卒中、外傷性脳損傷、脊髄 損傷、骨関節疾患、関節リウマチ、切断、神経・筋疾患、小児疾患、呼吸器疾患、心疾患、がんなどが含まれます。
公益社団法人 日本リハビリテーション医学会
このように内科系・外科系を超えて、臨床医学のほとんどすべての分野と関わる診療科は少ないと思います。リハビリテーション医療はチームワークです。リハビリテーション科医は幅広い医学的知識の習得と同時に特定の専門領域の知識を一層深めることが可能であり、また求められています。
現在、専門医の数で割ると圧倒的に医師が足りないのは、リハビリテーション医と救急医と言われており、実際どこのリハビリテーション病院に聞いても医師が足りないとの話が絶えません。
リハビリテーション医療そのものの認知度の向上と必要性から、リハビリテーション医を目指す若者が増えているようにも思いますし、加えて女性医師の増加、特に外科領域などでの女性医師の増加に伴い、ワークバランスなどの観点からもリハビリテーションに興味を持って下さる方が少しでも増えればと思います。
アクセス
- 所在地:
〒173-8605 東京都板橋区加賀2-11-1 - 交通アクセス :
帝京大学医学部附属病院の交通アクセス - 受付時間:
10:00~15:00